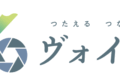From a distance 3. 橋本 弘道

「まあ、いいか」のその先に
自宅で仕事をしていると、日に1度か2度は宅配便が届きます。通販で購入した品だったり、定期配達を頼んでいる食品だったり、ものは様々ですが、玄関のドアを開けて「○○さんですね?」と家族の名前を言われれば、「はい、そうです」と答えてそのまま受け取っています。
小学生のころ、留守番をしていたときに自宅に届いた品物の包装を勝手に開けて、父親からひどく怒られたことがあります。お菓子のようなものを期待していたら高級ハムのセットだったので、興味をなくして玄関にそのまま置いておきました。帰宅した父は、送り主の名前を見て顔色を変えて私を叱り、包み直して送り返すために翌朝郵便局に出かけて行きました。
父は、税務署に勤めていました。送り主は当時、税務署に相談に来ていた会社の関係者でした。お中元やお歳暮の時期になると、父親が自宅にいるときは、配達してきた郵便局の職員に「これは受け取れません」と言って返送してもらうことが何度もありました。それほど高額の品でもないのだから受け取っておけばいいのに、と子ども心に思いましたが、40歳代前半で税務署をやめて独立するまで、父はこのスタンスを変えませんでした。
私が新聞社の社会部で警視庁捜査二課を担当していたとき、汚職が専門の捜査員に聞いた話があります。「贈賄で摘発される業者はね、最初はちょっとした贈り物から始めるんだよ。もらった方は、このぐらいなら、まあいいか、と思って受け取る。次は、食事にでも行きませんか。その次は……。で、泥沼にはまってしまう」
このぐらいならいいだろう。自分だけなら大丈夫だろう。そう思うことは、仕事でも日々の生活でもしばしばあります。新聞社時代の仕事について言えば、取材を終えて記事を書き上げ、締め切り間際に読み返して曖昧な点があるのに気づいたとき、「大丈夫だろう」という気持ちと「確認をとった方がいい」という気持ちのせめぎ合いが起きます。時間がないし、取材先にはすでに追加で何度も聞いているから、また問い合わせをするのは気が引ける。でも、そこを敢えて聞かなければ仕事としては完結しません。
そうまでしても結果的に誤報が防げるわけではありません。ただ、情報を扱うプロとして、そこをうやむやにしていたら、何であれ最後まで「まあ、いいか」で済ませてしまっていたように思うのです。
被害者の社員よりタレントを優先した放送局の幹部の件も、少し前にニュースになった会食のお土産に10万円の商品券が用意された問題も、最初にその話が出たときに「やめましょう」と言った人が周囲にいなかったのか、いたのに聞く耳を持たなかったのか。
「まあ、いいか」という空気に同調することもときには必要でしょう。ただ、様々なことをAIに任せておけば平均点以上、ときにはかなり秀逸な答えを出してくれる時代になって、人間にしかできない判断を求められたときは、易きにつくのだけは避けたいと思っています。